9月 27日 令和7年新盆法話
お疲れさまでございます。
お時間を頂戴してお話しをさせていただきます。
まず、ご一緒に南無帰依仏、南無帰依法、南無帰依僧とお唱えいただきます。お渡ししましたプリント、言の葉1に書いてあります。
私が先導いたします。この戒尺の音に続いて、お唱えください。
では、姿勢を正して、合掌をしてください。
南無帰依仏 南無帰依法 南無帰依僧
ありがとうございます。
今日は新盆のお参りということで、大きなお悲しみと痛みを抱えてのお集まりの方も多いでしょう。
その悲しみや痛みを 少しでも撫でることができればいいな、と願いながらお話をさせていただきます。
これから、お話を進めます前に、皆さんに一つお願いがございます。
どうぞ、姿勢を正して、目を閉じていただきたいのです。
そして、今年、新盆で迎えます方のお姿、お顔を、まぶたの裏に思い浮かべてください。
少しお時間をお取りいたしますので、心の中で、その人のお名前を呼びかけ、その人に語り掛けてみてください。
ありがとうございます。目をあけてください。
どうですか?
その人は、微笑んでおられましたか?
それとも、少し疲れたお顔や寂しそうなお姿をされていたでしょうか?
今日の皆さんの中には、ご両親のどちらかを亡くされてここに集われた方もいれば、もしかしたら、ご両親共にお別れされたという方ももいらっしゃるかもしれません。また、お連れ合いと死別されたという方もいれば、お子さんを看取られた方もいるかもしれません。
申すまでもなく、人の別れも一様ではありませんね。
それぞれに特別な別れであり、皆さん自身にしか味わえない経験をされたはずです。
だからこそ、大切な方とお別れして、お辛いですね、悲しいですね、という言葉だけでは足りないでしょう。響かないでしょう。
でも、今日、私はこの時間をお借りして、皆さんに、一つの物の見方を届けたいと思うのです。
まず、結論から申し上げます。
それは、人生というものは痛みばかりではないのですよ。人生には、恵というものがあるのですよ、とお伝えしたいのです。
大切な人と死別されて、生きていくのが辛いという方、その人との死別が、頭ではわかっているのだけれども、心が追っつかない方、そして、なんで自分ばかりがこんなに寂しく、悲しい想いをしなくてはならないのかと思い悩まれている方もいらっしゃるでしょう。
でもね、そんな皆さんにこそ、お伝えしたいのです。
それは、人生には、大きな痛みを通してでしか出会えない恵があるのだ、と。
人生には、大きな痛みを通してでしか出会えない恵があるのです。
令和5年の5月のことでした。
拙寺のお檀家さんで、37歳のご主人が亡くなりました。
交通事故でした。昼間、彼は自転車に乗っていた。そこを車にはねられたというのです。
2日間、家族、親族は奇跡を祈りました。しかし、彼は息を引き取りました。奥様と間もなく1歳になる息子さんを遺されての旅立ちでした。
葬儀の日、実は、、、息子さんの誕生日でした。
その日、家族三人で東山温泉に一泊で出かける予定だった。
おそらく、亡くなったご本人自身、まさか自分がこんなふうに亡くなるとは、まさか自分がこの日に旅立つとは微塵も思ってなかったでしょう。
混乱し、取り乱す奥様は「信じられないし、信じたくない」と何度も仰りました。
通夜や葬儀の時、父親の死を理解できない息子さんを見て、参列された多くの人が涙を流されました。
人生というのは、一面において、とても残酷です。
その日、その時間、その場所にいなければ、事故に巻き込まれることはなかったでしょう。
いや、わずか数分でもずれていれば、、、もし、仮に事故に遭ったとしても、車のスピードが緩ければ、、当たった角度が異なっていれば、、、
いくら考えても、取り返しがつきません。
起こってしまったことは、起こしてしまったことはなかったことにはできないのです。
人生には、もう一度やり直せることと、そうでないことがあります。
こんなふうに、途方に暮れて立ち尽くすしかないような経験をすると、心の底から、神も仏もあるものか、と思ってしまう時があります。
でもね、私は思うのです。
それでも生きていく、それでも生き抜いていく、それがお釈迦様の教えだと。
どんなことがあっても、生きてなさい。
辛くても悲しくても、格好悪くても、生き抜いていきなさい、それが、お釈迦様の教えだと思うのです。
なぜならば、生き抜いていけば、必ず、真実なるものと出会うことができる、のだとお釈迦さまは説かれています。
だからこそ、私たちには、大切な人を失ってみて、はじめて気づく世界があるのです。躓いたからこそ、開ける世界があるのです。
もちろん、それを手にするのは、とても困難なことです。
しかし、私たちは、その恵を手にする力を持っていることを忘れてはならない。
今年の5月、あのご主人の3回忌がありました。
あの時のお子さんは、3歳になっておりました。
ご主人との死別のあと、奥さんは仕事を探し、お子さんを保育園に預けながら、親子二人で暮らしているそうです。
3回忌の法要中のことでした。
お経をよみながら、私は、涙がこぼれそうになりました。
3回忌の法要の中で、奥さんが、息子さんを抱きかかえながら、お焼香をしました。その時のことです。
3歳の息子さんは父親のご遺影に向かいながら、自らが小さな手をあわせ、、、、目を閉じ、何かを念じているような、父親に何かを誓っているかのような顔をしていました。
そして、にっこりと微笑んだのです。
1歳になる直前に死に別れた父親を、3歳の子供がわかるのか、わずか3歳の子が、何を念じ、何を誓ったのか、、、、それを言葉にする力は、私にはありません。
けれども、その姿を見て、私は思ったのです。
彼は、決して不幸な子どもではない。 もちろん、早くに父親を亡くしたばかりに、抱えなければならない苦労もあるでしょう。
しかし、思うのです。彼が父を想い、手を合す時、父親はいつも彼の傍らにいて、彼を護りつづけてくれる。
そして、思うのです。 父親は37歳で人生を終えたけれども、子どもと触れ合う時間はたった1年間しかなかったけれども、決して、可哀そうな父親ではなかったんだ、と。
なぜならば、私たちの思念、、思い念ずることですが、私たちの思念や願いは、時を超えることができるからです。だから、彼は、息子さんの成長を、きっと見届け、息子の姿を片時も忘れることはない。
私たちの人生は、一見、不幸に思われるような事柄に出遭ったとしても、それを丁寧に受け止めれば、その痛みから大きな恵みを手にすることができる。 だからこそ、生きる。生き抜いていく。
今年、新盆を迎える皆さんと共に味わっておきたい詩があります。言の葉2をご覧ください。
これを読まれて、ああなるほどなと膝を打たれる方は少ないでしょう。でも、わからなくてもいいのです。
この真実に触れることが、あなたの人生に対する態度を深くし、また、亡き人への供養となる。
だから、どうか思いだした時に、手に取っていただきたい。
この詩は、内山興正老師が、仏教の、曹洞宗の、生まれ死んでいくこの命というものを、言語化されたものです。
私が先導しますので、声に出しましょう。
生死
手桶に水を汲むことによって
水が生じたのではない
天地一杯の水が
手桶に汲みとられたのだ
手桶の水を
大地に撒いてしまったからといって
水が無くなったのではない
天地一杯の水が 天地一杯のなかに ばら撒かれたのだ
人は生まれることによって
生命を生じたのではない
天地一杯の生命が
私という思い固めのなかに 汲みとられたのである
人は死ぬことによって
生命が無くなるのではない
天地一杯の生命が
私という思い固めから 天地一杯のなかに ばら撒かれるのだ
ありがとうございます。
大切なあの人を偲ぶ静寂の時、思いを凝らして あの人との出会いを喜び そして、別れに学ぶお互いでありたいと思います。
みなさんの大切な方は、皆さんの菩提寺、○○寺さんのご住職が、ご戒名を授け、そして、ご葬儀をしました。
つまり、仏教で葬式をし、ご戒名を授かったからには、その人は遠くに行ってしまったのはない。
その人は、跡形も消えてなくなったのではない。
どうかこのお盆の期間。
お迎えする方のお姿、お顔を、佇まい、気配を感じ取ってあげてください。
あなたと共に過ごした時間を、親しく思い直してください。
そして、お盆が終わるとき、その方にたいして、別れて悲しいけれど、寂しいけれども、でも、ここから、もう一度、頑張るよ、とお伝えください。
※ 山頭火
お時間を頂戴いたしました。
穏やかなお盆をお過ごしください。
【普回向】



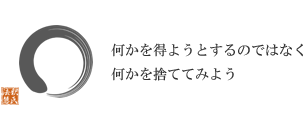

コメントはありません