9月 13日 今日の米 今のパン
安心と書いて、あんじん、と読む。
心の落ち着きどころ、自分の核となるもの、自分が自分である理由、、、そんな意味だろう。
しかし、現実の暮らしは、今日の米、今のパン。
安心というものがあるとは、夢にも思わず。
たしかに、お腹がすいてりゃ、安心もないのかもしれない。
そりゃ、経済的な困窮から抜け出すには、なによりもお金だろう。
平日の昼間、女性から電話があった。
「お願いします。50万円、貸してください。助けて下さい。」
檀家さんでもなく、知人でもなく、、、お会いしたこともない人だった。
見ず知らずの人だからこそ、吐けた言葉なのかもしれない。
示して云く、故僧正建仁寺におはせし時、獨りの貧人來りて云く、我が家貧ふして絶煙數日におよぶ。夫婦子息兩三人餓死しなんとす。慈悲を以て是れを救ひ給へと云ふ。其の時房中に都て衣食財物等無し。思慮をめぐらすに計略つきぬ。時に藥師の像を造らんとて光(クワウ)の料に打のべたる銅少分ありき。是れを取て自ら打をり、束ねまるめて彼の貧客にあたへて云く、是を以て食物にかへて餓をふさぐべしと。彼の俗よろこんで退出しぬ。時に門弟子等難じて云く、正しく是れ佛像の光なり。これを以て俗人に與ふ。佛物己用の罪如何ん。僧正の云く、誠に然り。但し佛意を思ふに佛は身肉手足を割きて衆生に施こせり。現に餓死すべき衆生には、設ひ佛の全體を以て與ふるとも佛意に合ふべし。亦云く、我れは此の罪に依て惡趣に墮すべくとも、只衆生の飢へを救ふべしと云云。先達の心中のたけ今の學人も思ふべし。忘るヽこと莫れ。『正法眼蔵随聞記』
要するに、、、、一人の男がやって来て、親子3人の飲まず食わずの窮状を強く訴え、救ってほしいと懇願した。
当時、建仁寺には分け与えるものはなかった。
栄西禅師は、仏像の光背用に少し取っていた銅板を「これを食べ物に変えるがよい」と分け与えた。
しかし、その振る舞いを、弟子たちは「仏物己用の罪」ではないのかと糾弾したのであった。
栄西禅師は、「私は地獄に落ちようとも、そうしないではいられない」と応えた。
佛は身肉手足を割きて衆生に施こせり。



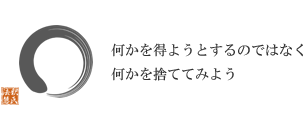

コメントはありません