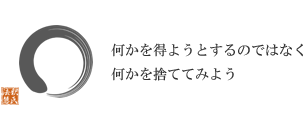作務衣に剃りあげた頭、頭陀袋を持つ私の姿を見て、「お坊さん?」と、乗り込んだタクシーの運転手が、勝手にしゃべり始めた。
昭和40年頃も、東京に出て働くのは当然の事だった、と。
その後は色んな職を転々として、今じゃあ、この年になってもタクシーに乗って稼いでるよ、と。
「曲がりなりにも家庭をもって、息子二人も独立して、今はかみさんと二人暮らし。
家を建てる甲斐性はなかったけど、それなりに楽しかったさ。
たまに見る孫の顔は、嬉しいね。なかなか、会いにこないけどさ。
競馬と酒ぐらいかな、あとは、何年かに一度、旅行する事かなぁ。
あのさ、お墓の事なんだけどさ・・・2年前、故郷のお寺に墓地を買ったんだ。
先祖代々は兄貴が守ってるから、自分たち夫婦のをね。
永代供養ってやつでさ。
息子たちに面倒をかけるのは嫌だし、自分たちの事は自分たちでしようと思ってさ。
かみさんも同郷で、やっぱり、故郷が恋しくてね。
そこのお寺ね、80歳を超えた優しい和尚さんでさ。
かくしゃくとしていて、村の人たちも尊敬してるんだよ。
ただ、跡取りの息子さんが事故で死んじゃって、その娘さんが大学を出たら跡を継ぐって話だったんだよなあ。
でもね・・その娘さんも事故でさ。
和尚さんは、ショックで入院したらしいんだよね。
もう年だしね、跡取りいなくなっちまって。
こんな場合、どうなるんだろう?
どこかから、新しい和尚さんが来てくれるのかな?
本山から派遣してくれるのかな?
兄貴から聞いたけど、檀家みんなが気にしているって。
そりゃそうだよなあ。
でもさ、田舎の小さな村だからさ、誰も来てくれないんじゃないかって。
住職さんも息子さんも学校の先生をしながら、お寺をしていたからね。
だから、誰も来てくれないんじゃないかってね。
でもこのまま、お坊さんが来なかったら、お寺やお墓はどうなるんだろう?
あのさ、どうなるの?」
心情的には何とか力になってあげたい。
けれどおそらく、現実的な処理が行われる。あるいは、政治的に解決される。
「どうなるのかな。でも、いい方向に転がっていくといいね」
牧師さんは、協会からの派遣で赴任するらしい。
だから、何年かに一度、布教の為に引越しをしなければならない。
11月 20日 僧形
先日、日本クリスチャンアカデミー関東活動センターで、「対話プログラム」の催しがありました。
テーマは、『死と葬儀 ~宗教はどう係る~』
講師は、雑誌「SOGI」の編集長の碑文谷創先生でした。私も応答者として参加いたしました。
碑文谷先生の講演<レジュメ有>
1、脆い死の時代 医療化した死の時代 非神話化した死の時代
2、看取りと葬送の問題点
3、宗教者の係わりと必要とされるサポート
時代背景や文化の規制を受けながらではありますが、葬儀の本質とは、いかに、死を受け入れるかであり、その葬送の形も変化する事を教えられました。
応答者ということでしたので、講演に対して、2・3の質問をすればいいのだろうと思っていたのですが、20分程度で、普段の活動を通じての問題提起をしてくださいと、司会の方に求められました。
そこで、出家の経緯や参禅の事、役僧の体験や葬儀・法事の思う事、僧侶や寺院の在り方について考えるところを述べました。
その後、全体の質疑応答のなかで、こんな問いをいただきました。
「供養という形において、<なんとなく落ち着かない気持ち>を利用して、お金儲けをしている宗教者が多いと思うけれども、その点をどのよう考えているのか」
この問いに対して碑文谷先生は、「寄り添う者」をキーワードにして、こんな体験を語られました。
ある日、僧侶との話し合いの中で、「斎場に行っても、遺族が挨拶にこないで、葬儀社が代わりにくることがある」と発言した者がいた。そこで即座に、指摘した。
「それは違う。あなたがた僧侶がまず遺族のところに出向き、話を聴くのが本来だ」
宗教者は遺族の悲しみの同伴者になることを考えるべきだ、と。
次に、マイクを渡され、私はこんなふうに答えました。
「とてもありがたい、厳しいご指摘です。
私自身は、その<なんとなく落ち着かない気持ち>を利用して金儲けはしないぞ、と覚悟をしております。
役僧を辞め、さぁどうしようと困った時、自分の中で芽生えた答えのひとつが、僧形として生きるでした。
つまり、お坊さんとして生きる事です。
じゃあ、そのお坊さんと在俗の方々との違いは何か?
それは、ものの見方だと思います。
参禅のお師匠様から叩き込まれたものの見方を、ご縁あるところで説き示す事だ、と。」
38歳、やっと、その歩みをはじめたばかり・・・
投稿日時 07:46
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
業を修めると書いて、修業。
学芸を習い修めるのが、修業。
一事を究めようと、一事に秀でようと、修練を重ねる。
和菓子職人になるための修業、小説家になるための文章修業。
習得がすめば、その修業は卒業できる。
行を修めると書いて、修行。
仏道や武道を修めるのが、修行。
一つ一つの行いを丁寧に修めていくのが、修行。
お寺で坐禅修行、技を極めたものが道場を巡って武者修行。
心掛け次第で、どこまでも深めていける。
鈴木正三が、弟子の恵中に示した。「修行とは、我を尽くす事なり」
「我を尽くす」とは?
自分の為に、懸命に励む事のように思うけど・・・
頑張っている俺には、褒められたい俺がいる。
努力している私には、認めて欲しい私がいる。
頑張りや努力のそばに、他人と比べる自分が顔を出す。
隣りを横目で覗く事でしか、自分を確認できない。
止むにやまれぬ思いから、禅門に飛び込んだあの日、お師匠様からこんな教えをいただいた。
「いま・ここ・一所懸命」 「他人と自分を比較する事をやめなさい」と。
慙愧に耐えないけれども・・・
我を尽くすとは、自分という塊に拘泥しない事。
我を尽くす時、実は、我ならざるものはない。
いま・ここに、全てがあった。
11月 04日 他己
投稿日時 20:08
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
夕方、かったるそうにレジを打つ30前の店員。
小銭を取り出すのに手間取っている老婆に、小さく吐き捨てた。
「うぜぇ、早くしろよ」
1時間なんぼの仕事にさえ、プライドが持てないのか?
こんな店員を雇い、使いまわして捨てるのも、これもまた、雇われの店長。
「母子家庭になったおかげで、市営住宅にも入れたし、手当ても結構、貰えるの」と、カウンターで、寿司をほおばりながら語る女。
「5年前に離婚届けをだしてさ、でも、実は、・・・ずっと、旦那と暮らしてるのよ、凄いでしょ。だって、こんな時代、真面目にやったら、貯金もできないわよ。
子供?いるわ。小学生と中学生の二人の息子」
利権目当ての偽装離婚。
その親の背中は、どんなふうに、子供に映るのだろうか?
くすねた金じゃあ、うまい酒は飲めやしない。
大きなバイクを買っても、任意保険に入らない理由は、「金がないから」
高級車を転がしても、娘の保育料を払わぬ親。
ブランド物のバッグを持つために、「援助」を求める女。
そりゃあ、いい物はいい。でも、本当はどうなのか?
消費による自己実現。晦まされた人の価値。
自由とはお金の事かい?
道元禅師は、他にも己という字をつけ、他己<たこ>と現した。
自分と他人ではなく、自己と他己。
自分と他人の二つではなく、己ひとつ。
ふたつの対立の世界ではなく、へだてのないひとつの世界。
己ひとつの世界だよ、と。
自分の物は俺の物、他人の物も俺の物とするのは、蛸野郎の論理。
他己、それは、他もまた己にほかならぬ事。
自己とは、自分に現れた己であり、他己とは、他に現れた己の事。
つまり、すべてが己。
己ひとつが解れば、老婆が己の姿と重なるだろう。
己ひとつが解れば、世間を騙す事は、己自身を騙す事に気付くだろう。
己ひとつが解れば、この命もその金も、預かり物だと知るだろう。
己ひとつの世界だからこそ・・・愛おしいのだ。
10月 31日 静寂
生死 内山興正老師
手桶に水を汲むことによって
水が生じたのではない
天地一杯の水が
手桶に汲みとられたのだ
手桶の水を
大地に撒いてしまったからといって
水が無くなったのではない
天地一杯の水が 天地一杯のなかに ばら撒かれたのだ
人は生まれることによって
生命を生じたのではない
天地一杯の生命が
私という思い固めのなかに 汲みとられたのである
人は死ぬことによって
生命が無くなるのではない
天地一杯の生命が
私という思い固めから 天地一杯のなかに ばら撒かれるのだ
『生死を生きる−私の生死法句詩抄』
大切なあの人を偲ぶ静寂の時
思いを凝らして あの人との出会いを喜び 別れに学ぶ
そして、あの人のたたえる寂けさによって
真実なるものに気付き、いのちのはたらきに目覚める事ができる
10月 20日 悲しみ
彼は8歳の時、父を亡くした。
母は、そののどぼとけを小さなガラス箱に入れた。
そして、毎朝一番に水を汲み供えるように、彼に命じた。
彼は、共同の井戸から15分以上かけて、その水を運び続けた。
かなしみはいつも 坂村真民
かなしみは
みんな書いてはならない
かなしみは
みんな話してはならない
かなしみは
私たちを強くする根
かなしみは
私たちを支えている幹
かなしみは
私たちを美しくする花
かなしみは
いつも枯らしてはならない
かなしみは
いつも堪えていなくてはならない
かなしみは
いつも噛み締めていなくてはならない
悲しみを受け止める事、そして、温める事。
悲しみから学ぶ視点こそが、大切ではないのだろうか・・・
投稿日時 14:11
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
先日、5歳になる姪にこんな事を質問されました。
「世界で一番、偉い人ってだれかな?」と。
どうでしょうか?
皆さんは、この世で、一番偉い人って誰だと思いますか?
政治家や弁護士、そして、お医者さん。そんな風に、ステータスとされる職業に就いている方を思い浮かべるかもしれません。
けれど、その職業や地位が偉いのか?その人が偉いのか?
また、そんな地位や肩書きよりも、もっと端的に、預金通帳の残高が多い人、或いは、財をなした人が偉いのだと、答える方もいるでしょう。
お金のあるなしだけで、人生の勝ち負けが決まってしまう、そんな時代でもあります。
お金は大切だけれども、お金が偉いのか、その人が偉いのか・・
私は、姪に逆に問いかけました。
「えりちゃんなら、誰だと思う?」
パパやママと答えるかなと思いましたが・・・
もし、法慧ちゃんと答えるなら、おもちゃでも買ってあげようと思っていましたが、その答えは「アンパンマン」でした。
予想外の答えに驚き、熱があるのかと彼女の額に手をやりながら、
「なんで、アンパンマンなの?」と尋ねてみました。
「だってね、アンパンマンって、すごくやさしいでしょ。
悪い事するバイキンマンをやっつけて、とっても強いし。
それに、おなかのすいた人には、自分の顔を食べさせちゃうんだよ。
だから、とっても偉いなって思うの」
と、そう語る彼女は真剣で、熱もありませんでした。
私は、アンパンマンを子供の漫画としか思っていませんでしたが、彼女なりに5年間生きてきて、この世で一番偉いのはアンパンマン、と答えるのには、何か根拠があるのだろうと調べてみることにしました。
アンパンマンの作者、やなせたかしさんは、皆さんご存じの歌『手のひらを太陽に』の作詞者でもあります。
やなせさんは、ご自身の生い立ちや戦争の体験をもとに、アンパンマンに、本当の正義とは何か、という思いをぶつけていたのだと知りました。
我が身を捨てる、我が身を献じる心なくして正義は行われないという思いから、アンパンで出来た顔が、欠けたり濡れたりするとその力を失うという弱点がありながらも、溺れそうな人を見れば、ためらわずに水に飛び込み、ひもじい思いをしている人をみれば、アンパンマンが自らの顔をちぎり食べさせる事によって、人を救うという姿を描いています。
アンパンマンは、再生可能な顔を持つから、そんな事ができるのだ、と見る人もいるでしょう。現実にはありえないよ、と言う人もいるでしょう。
しかし、その道を歩むと決めた者にとっては、いくら挫折したとしても、たとえ、志半ばで倒れたとしても、やはり、それを貫かないではいられないと思うのです。
やなせさんは、この作品を通して、何のために生まれて、何のために生きるのかを問い続けています。あなたは、何のために生まれて、何のために生きるのか?
彼女がアンパンマンを偉いと感じたのも、やなせさんの願いに響いたからでしょう。
お釈迦さまは、このようにおっしゃっています。
「人は、地位や生まれ、姿によって、偉いのではない。
その人の行いによって、賤しい人ともなれば、偉い人ともなる。」
その人の行いによって、決まる。
では、その行いとは、なんでしょうか?
やなせさんの言葉を借りれば、何のために生まれて、何のために生きるのかの答えこそが、行いであります。
そして、行いとは夢であり、誓いであり、願いである。
すなわち、人生とは、夢を生きることであり、誓願を生きることだと言えます。
地位や名誉や、お金があるかないか、は結果です。
結果のみを見ることより、むしろ、今どのような夢や誓願を抱いて生きているのかを、問わなければならない。
今年の夏、ある経営コンサルタントの方とお会いするご縁がありました。
名刺を交換した直後、いきなり、彼がこんな事をいいました。
「この鞄の中に3億円があります。
これをあなたに差し上げると申し出たら、どのようにお使いになりますか?」
私は、「坐禅堂を建てます」と、即答いたしました。
私は、二十歳の頃、大切な方との別れがありました。
それが契機になり、禅の世界にひかれていきました。
はじめて訪れたお寺に、坐禅堂がありました。
そのお寺の方丈様は、共に、坐る事を許してくださいました。
結果、そのご縁で頭を剃る事にもなりました。
あの頃の私と同じ人のためにも、坐禅堂を作り、共に坐る場を作りたいと願っております。
結局、3億円はいただきませんでしたが、彼は笑いながらいいました。
「この質問を経営者の方々にしますが、多くの方が貯金をする、と答えます。
貯金をして、しばらく使い道を考えます、と。
慎重になるのは結構ですが、でもそれはちょっと違うな、と思うのです。
今、本当に夢を生きていれば、正しい願いを生きていれば、答えられるはずです」
夢や誓願を生きるとき、仏教徒として忘れてはならない誓いがあります。
一切の悪いことは誓っていたしません。
一切の良いことを誓っていたします。
すべての人のため、社会に尽くすことを誓います。
この誓願の原点は、すなわち、南無帰依仏であります。
仏に帰依すると信じたときに、我が仏である、と気づいた時、自ずとこの誓願が体に表れてくる。
人のため、世のために、この身を尽くさないでおられない。
それは、叱られたくないから、捕まりたくないから悪いことをしない、というものではありません。また、褒められたから、他人に良く思われたいからいいことをする、のでもありません。
泥棒は、盗めば泥棒です。
警察に捕まらなくとも、検察に起訴されなくても、裁判で実刑を受けなくても、盗めばそれは泥棒です。そんな世間の取り決めややりとりではない。
でも、難しくはない。
アンパンマンにも出来るし、5歳の女の子にも、その尊さは理解する事ができる。
だからこそ、共に、南無帰依佛と手をあわせ、この誓願を持って、本当の偉い人となる歩みをいたしましょう。
一切の悪いことは誓っていたしません。
一切の良いことを誓っていたします。
すべての人のため、社会に尽くすことを誓います。
ご清聴ありがとうございました。
9月 30日 合掌
投稿日時 00:46
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
福田さんが総理大臣となりました。
残念ながら、安倍さんは、美しい国を作らずに終わってしまいました。
美しい国というのは、人のために手間をおしまない事であり、惻隠の情や温かな情愛を感じる感受性を育てる事であり、ひいては人間としての尊厳を守るという事じゃないかと思うのです。
子が親を、親が子を殺す家庭が増えてきました。
また、その場に居合わせたがために、命まで奪われてしまう事件が起きています。
物があふれ、一見、平和で豊かな国となりながらも・・・
大切な何かが失われたからだ、と多くの方々が指摘します。
しかし、それが何かなのか?
その何かとは、その何かのひとつとは、私は合掌であると思うのです。
静かに手を合わせ、感謝し祈りを捧げる時間を取り戻せる場所がお寺。
人間としての尊厳、また、いのちの大切さに気付くためにも、お寺にお参りをする。
ご本尊様に静かに手を合わせる。ご先祖様に感謝の気持ちを捧げる。
そんな時間を持つ事によって、本当の豊かさに気付く事ができる。
そんな時間を持つことによって、合掌を生活に取り入れる事ができる。
見直そう 合掌の心 伝えよう 合掌の姿
あなたのその手は、銃を持ち自らを打ち抜くために、あるのではない。
あなたのその手は、ナイフを持ち人を傷つけるために、あるのではない。
斧を持ち父を、紐を持ち母を、ビール瓶を持ち弟子を・・・殺めるためにあるのではない。
金をくすねるために、女を犯すために、物を奪うために、あるのではない。
その手は・・・合掌するためにある。
9月 24日 慈経
「政治とは生活」と宣言する政党もある。
「宗教とは生活」と宣揚する宗派もあってよさそうものだ。
よく教えの道理を会得したる者が
自由の境地を得てのちになすべきことはこれなり
有能、率直、そして端正なること
よき言葉を語り、柔和にして、高慢ならざること
足ることをしりて、養いやすきこと
雑事にかかわらず、簡素に生きること
五根をきよらかにして、聡明、謙虚なること
檀越の家におもむいて貪りなきこと
汚れたる業をなして識者の非難をうくることなかれ
ただ、かかる慈しみのみ修すべし
生きとし生けるものの上に
幸いあれ、平和あれ、恵みおおかれと
たとい如何なる生を受けし者も
恐れにおののく凡夫も、悟りて恐れなき聖者も
丈たかき者も、その身大いなる者も
中ほどの者も、小さなる者も、いうに足らざる者も
目に見ゆるものも、見えざるものも
遠くにあるものも、近きにあるものも
すでに生まれし者も、やがて生まれくる者も
生きとし生けるものの上に幸いあれ
たがいに他者を欺くことをせざれ
いずこ、なにものにも、軽賎の思いをいだくなかれ
憤りにかられ、あるいは、憎しみのゆえに
他者の苦しむをねがうべからず
あたかも母たる者がその独りの子を
おのが生命をかけて守るがごとく
すべて生きとし生けるものの上に
限りなき慈しみの思いをそそげ
まことに、一切の世間のうえに
限りなき存在のうえに、この思いをそそげ
高きところ、深きところ、また四方にわたり
怨みなき、敵意なき、限りなき思いをそそげ
立つにも、行くにも、坐すにも、臥するにも
いやしくも眠りてあらざるかぎり
力をつくしてこの思いを抱くべし
ここに聖なる境地というはこれなり
「慈経」『スッタ・ニパータ』
南方仏教において、この経典はいつでもどこでも唱えられてるそうです。
投稿日時 09:12
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
この物語は、南アメリカの先住民に伝わるお話です。
森が燃えていました
森の生きものたちは
われ先にと
逃げていきました
でもクリキンディという名の
ハチドリだけは
いったりきたり
くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは
火の上に落としていきます
動物たちがそれを見て
「そんなことをして いったい何になるんだ」といって笑います
クリキンディは こう答えました
「私は私にできることをしているだけ」
『ハチドリのひとしずく いま、私にできること』
今日の一滴って、何だろう?
着飾って、勝負下着で彼とのデート。
子供を連れて、勝沼にぶどう狩りへ。
入院してる旦那のお見舞い。
溜まった洗濯物を片付ける事、散らかった部屋に掃除機をかける事。
受験にむけてのお勉強、留学のための手続き。
いま・ここ、そして、この私。
全てはいま・ここにある、と覚悟ができた時、今まで嫌で嫌でたまらなかった自分や、自分を取り囲む環境も、あなたの味方に変わる。
さて、あなたの一滴って、何だろう?
その一滴が、真っ直ぐに、いのちの大河に続きますように。