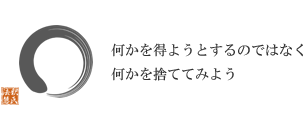投稿日時 19:07
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
その若者は、かつて、とある宗教に帰依していた。
しかし、お釈迦様の教えに出合い、帰依し、出家した。
面白くないのは、かつてのお師匠さん。
大切な弟子をたぶらかした、とご立腹。
お釈迦様のもとを訪れ、激しい悪語をもって、罵倒し、誹謗した。
けれど、お釈迦様は、ただ黙していた。
そこで、お師匠さんは、大威張りで言い放った。
「沙門よ、なんじは負けたのだ。沙門よ、わたしは勝ったのだ」
すると、お釈迦様は、静かに答えた。
「雑言と悪語とを語って、愚かなる者は勝てりと言う。
されど、まことの勝利は、堪忍を知る人のものである。
忿<いか>るものに忿りかえすは、悪しきことと知るがよい。
忿るものに忿りかえさぬ者は、二つの勝利を得るのである。
他人のいかれるを知って、正念におのれを静める人は、
よくおのれに勝つとともに、また他人に勝つのである」
これを聞いたお師匠さんは、猛反省。
やがて、機縁が熟し、お釈迦様のもとで出家したという。
いくら、声が大きても、いくら、すごんでみせても・・・それは、虚勢。
他人に自分の考えを押し付け、折伏したとしても・・・それは、まやかし。
勝者は、どっち?
投稿日時 03:13
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
たとえ、あの声が聞こえなくとも、話しかけたい
たとえ、あの人が食べなくとも、美味をお供えしたい
たとえ、喜ぶ顔が見えなくとも、お花とお香をお供えしたい
・・・いっしょに、いるからね。
投稿日時 06:10
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
おめでとう、よくがんばったね。
約束どおり、ちゃんと、お母さんのお腹の中にいてくれたね。
お父さんから、さっき、電話があったよ。
「母子ともに健康です。俺も妻も、俺の両親も妻の両親も、みんな、泣いています。ありがとうございます」
どうだい?目に映るものは?この国の感じは?この時代の空気は?
やって、いけそうかい?
でも、絶対に、逃げてはダメだよ。
随分辛い思いもして、やっと、この国に、この時代に、この親のところで、ご縁が熟して現れたんだからね。
やよあか子汝れはいづちの旅をへて
われを父とは生れ来ませし
吉川英治『川柳詩歌集』
【意訳】
やあ、ようこそ。ようこそ。
生生世世、長い時間をかけて、生まれ変わり死に変わりしながらも
私との深い深い因が生まれ、育まれ、時を得て、今・ここに、縁が熟した。
だからこそ、私を父親としてこの世に誕生したんだね。
どうぞ、よろしくね。
目に映る物しか信じない人が多い時代だけれども・・・
生きる意味や人生の目的を見失わせる罠の多い時代だけれども・・・
悲しい出来事に襲われたとしても
辛い立場に追い込まれたとしても
病気や怪我に悩まされたとしても
生きていてつまらなくなったとしても
大切な人との別れに心を乱されたとしても
もう死んでしまいたいと思う事があったとしても
そして、生の呻きを体験する感性を持ったとしても
でもね・・・忘れてはいけないよ、逃げちゃダメだって事。
絶対に、絶対に、大丈夫だからね。
大きな大きな、たとえようもない大きな、このいのちの煌きの中で、
君は、この父母を縁として、人間として命を授かり、その体を預かったのだ。
だから、命は、この大きな大きないのちに護られどおしに護られている。
絶対に大丈夫、心配いらないよ。
君の名前は千尋<ちひろ>、気に入ってくれるかな?
千とは、たくさんという意味。つまり、たくさんの人と出会い、たくさんの本を読み、たくさんの場所に行き、たくさんの体験をして欲しい。
その中で、きっと、真実の在りかに気付く事になるだろう。
そして、その真実の在りかを一人でも多くの人に伝えて欲しいんだ。
君なら、きっとできるよ、千尋ちゃん。
8月 04日 直葬
直葬<ちょくそう>という言葉を知っていますか?
産地直送の事では、ありません。
お通夜も葬儀も告別式もせずに、直接、火葬場でお別れするスタイルの事。
死亡した病院や自宅から、火葬場へ直行。
直葬の直は、直接の直なのか、直行の直なのかは、直情径行の直なのか・・・不勉強のためわかりません。
火葬の際に、炉前でのお経を頼む人もある。
10分程度のお経で5万円が相場。別途、交通費やお膳料も請求。
もちろん、ご紹介のお坊さんは薄情で、収骨まで一緒にいてくれない。
直葬の直は、お坊さんの直行直帰の直、お布施を貰えば直ぐに帰るの直、なのかもしれませんね。
この直葬が増えている傾向にあるらしい。
故人に家族や身よりがいないからという理由だけでなく・・・
家族の絆の弱体化や地域社会との関係が希薄になった点。
この世限りの人生、俺様一人の人生という人生観の蔓延。
先祖観の変化、つまり、先祖は親か祖父母くらいまでという考え。
そして、菩提寺を持たない人の増加。
例えば、長期にわたる医療や介護にお金がかかり、葬儀をするお金が残っていない事情もある。
例えば、子供に迷惑をかけたくない、あるいは、お葬式に大切なお金を使うのなら可愛い孫に残してあげたい、と願う人情もある。
直葬の根源は、葬儀や僧侶に対する不信感。
マスコミは葬儀は金がかかるものと喧伝し、騙されたの体験談ばかり。
葬儀社は価格競争にはしり、お得感と感動を売り物にする。
坊主が勝手に付けた戒名は高額であり、その意味すら教えてくれない。
赤や黄のべべを着て、有り難くもない儀式以下のショーを見せつけられる。
そして、参列者が多くなればなるほど、損をするかのような錯覚・・・
本当は、手ぶらで焼香に来る人などいないのに。
そして、不信感は拒絶に変化した。
悪しき因習の踏襲は避けて然るべきだけれども、しかし、安易な選択は、後に、迷いを残す結果にもなる。
短絡的思考の持ち主は、案外、霊の指摘には弱く、程度の低い自称霊能者にたかられる。
現実に、意識の低い悪徳葬儀社だっている。
現実に、品も学も自戒も法力もない坊主だっている。
しかし、そのことを葬式の時に、はじめて気付いたとしたら、・・・お気の毒だけれども、それは、あなたの怠慢でしかない。
なぜなら、葬儀社の情報や評判は、たやすく手に入る。
僧侶の人品を知らないのは、日頃、お寺にいかない証拠。
現今の仏教は葬式仏教と揶揄されて久しい。
しかし、葬式仏教というのは、僧侶だけではなく、身内が死んだ時にだけ寺院に頼むという関係、平素は仏法に無関心な者をも批判している言葉。
人が亡くなると家族に負担をかける事は間違いないが、それが迷惑かどうかは、生前の家族関係次第。
人は、生まれる時も死ぬ時も、金はかかる。
葬儀に見栄は必要ない。
大切にしなければならない事は、潤いのある別れの時間。
「自分は直葬でいいよ」と、両親に言われたら・・・あなたは、どう答えますか?
新しく永代供養墓を作って売り出すという人に会った。
跡取りのいない家庭がターゲットだそうだ。
いやね、結婚しないのもいれば、子供を作らない夫婦もいるだろ。
こんな社会情勢じゃ、檀家制度も長くはねえからな、と、したり顔。
で、どう供養するのですか?と問えば・・・
そりゃ、永代供養墓と合祀墓を作って売るのよ。
予算がなけりゃ、最初から合祀墓に入ってもらってさ。
もっとも、永代供養墓に入っても、33年経てば、合祀墓に引越しをしてもらう事になるんだけどさ。
こちらでは、永代供養とは、33年のご契約。
お葬式費用一式、戒名の料金、33年間分の護持会費、付け届け、年忌法要のお布施、塔婆料金、お施餓鬼、等々のお支払いは、一括払い。
永代とは33年ですか?とお伺いしたら・・・
だって、きりがねえじゃねえか、と、あっさり。
けど、33年以上の物を納めてくれるのなら、話は別だけどさ。
じゃあ、いつ供養するのですか?と尋ねたら・・・
そりゃ、お盆のお施餓鬼の時にでもまとめてやるのよ、と、きっぱり。
俺は金にならねぇお経は読まない事にしてるから、朝課も晩課もしねぇよ。
お前もよく考えなよ、って、言われたけれど。
お前も阿呆な考えはやめて、ここで役僧をしなよ、って、説教されたけど。
結局、青臭い想いが邪魔をして、お断り。
もし、跡取りのない人が、お墓の事を思い悩んでいるのなら・・・
もし、身寄りのない人が、自分の最期を気にしているのなら・・・
・・・やっぱり、銭や金の事など言わずにさ、そろばん勘定なんてしなくてさ、その人の事を慮ってさ・・・だって、頭を剃ってるのだからさ・・・
「何も心配いらないよ。お寺が続く限り、護るからね」
「何も心配いらないよ。お寺が続く限り、供養するからね」
投稿日時 21:02
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
サイパンには、日本が委任統治した歴史がある。
そして、1944年7月7日サイパン部隊は玉砕。
サイパン島の最北端の岬、マッピ岬。
千名を超える人々が、80メートルの断崖絶壁の岬から身を投げた。
飛び込めない子を絞め殺し、共に逝く人。
生まれて間もない子を、体に縛りつけて飛び込む母。
水面には、鮫の群れが見えたという。
この島で、日本に一番近い場所を、死に場所にした誇り。
狂わんばかりの恐怖を、絶体絶命の絶望を、悔しさと命の呻きを、
「天皇陛下万歳」と、大きな声で叫ぶ事で、全て、押し殺した。
その場所が、バンザイクリフ。
今そこには、多くの慰霊碑や塔婆が並ぶ。
海底にも、慰霊碑があるそうだ。
そして、ダイビングスポットでもあるらしい。
先の戦いにおいて、仏教者の多くが戦争を支持したという批判。
不殺生を説くべき者が、何故に、体制側にこびたのか、と。
私の中で、未だ、確かな答えはないけれども・・・
徒に、平和を叫ぶよりも、この涙の中に、僧侶として在りたい。
この恐怖の中に、この絶望の中に、この悔しさと呻きの中に。
ご縁あって、本日からサイパン 今でこそバカンスの島なれど・・・わずか半世紀前は、多くの人が泣いた島 帰宅予定は15日
袖ふりあうも 多少の縁
恋焦がれたあの娘に袖にされ、多少の縁さえもないものなのか・・・
と、頭を抱えた純な中学生でした。
正しくは、多少の縁ではなく、他生の縁であり、多生の縁であると知った。
袖ふりあうも 他生の縁
今生<こんじょう>は、この世の事。
他生<たしょう>とは、前世や来世の事。
輪廻の中に、幾たびも生まれ変わり死に変わりする故に、多生。
悠久の時の流れの中で、いま・ここに、ご縁が熟して、ご縁が現れた。
・・・だから、あなたと、出会えた。
投稿日時 19:57
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
生まれてくる子に名前をつけて欲しいと頼まれたのが、3月。
36歳で初産。予定日が8月との事。
男と女の連れ合いが父と母に変わり、命の前にひざまずく。
激しいつわりもなく、経過は順調のように思えたけれども、5月に緊急入院。
早産の危険がある、と。
もう、この病院では手に負えないからと、転院をしたのが6月はじめ。
喜びが不安に負けそうになり、胸が張り裂けそうな時を過ごす。
もしや、とおののきながら、ただ祈る日々。
自分が代われるものなら、代わってあげたい、と切に願う父。
自分の命はどうなっても、この子だけは守りたい、と切に願う母。
・・・父と母と子が、ひとつの家族になれた瞬間。
ねぇ、君。
君のお父さんとお母さんは、今、君を授かった喜びをかみしめながら、
命懸けで、君を守ろうと真剣に全力で戦っているんだよ、わかるだろう。
あと、3週間。いい子にしているんだよ。
そうすれば、きっと、とても素敵な事があるからね。
そうそう、お釈迦様がこんな話をしてるよ。
大海の底に一匹の盲亀がいて百年に一度、波の上に浮かび上がる。
その海に一本の浮木が流れていて、その木の真中に一つの穴がある。
百年に一度浮かぶこの亀は、この浮木の穴から頭を出せるだろうか?
これは、難しい事だよね。
けれども、実は、この世に生まれる事はもっとたいへんな事なんだって。
じゃあ、大地の土と、爪の上にのせた土とどちらが多いと思うかな?
大地の土の方が多いよね。大地の土はいのちの事。
そのいのちが、人として命を享けるのは、爪の上の土ぐらい少ないんだって。
・・・命を授かる事を、当たり前のように思ってしまうけれども、
本当は、簡単な事ではないんだ。
人間の世界の有り様を観ずれば・・・
好きで生まれてきたわけじゃないと、ほざくガキもいる。
家や親を選んで生まれてきたかったと、のぼせる阿呆もいる。
やっとの思いで、生まれ育てられた命を捨てる人もいる。
育児放棄し虐待する親もいれば、聞き分け出来ない子もいる。
しかし、人は願生し、娑婆国土しきたれり。
私たちは、願って願って、願われて、その願いが叶って、人として生を享けた。
私たちは、願って願って、願われて、その想いが通じて、この世に生を享けた。
ねぇ、君。そうだよね。
今の君なら、わかるよね。このいのちの在り方が・・・
大丈夫だからね。絶対に、大丈夫だよ。
まことに、人間は生まれながらに、口中に斧を生やしている。
愚かな人は悪口を語っては、それで自分自身を斬っている。
『スッタニパータ』657
デンタルケアもオーラルケアも大切だけれども・・・口中の斧に気付く事。
危険!この斧は、よく切れます。