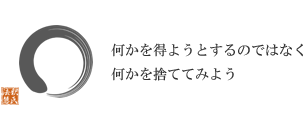知恵とは、物事の道理を判断し、処理していく働き。
物事の筋道を立て、計画し、正しく処理していく能力。
自分のみを良しとする時、己のみを高しとする時、
小賢しさが顔をもたげ、知恵は悪知恵となり人を傷つける。
ふたつに分ける二元的なものの見方は、執着を生み、苦の原因となる。
仏教では、知恵とは書かずに、智慧と書く。
摩訶般若心経の般若とは、智慧の事。
物事をありのままに把握する真実なる眼。
本当は・・・無眼耳鼻舌身意。
眼が無く、耳が無く、鼻が無く、舌が無く、身が無く、意が無い人は誰?
私という塊はない。
ひとつの世界。分け隔てのない世界。
投稿日時 20:54
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
神よ、
変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれらに与え給え。
変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷静さを与え給え。
そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、識別する知恵を与え給え。
ラインホールド・ニーバー <大木英夫 訳>
米の神学者、倫理学者ラインホールド・ニーバーが教会で説教したときの祈りの言葉。
この言葉は、神学者フリードリッヒ・オーティンガーの作という説もあれば、古代アラビアから伝わってきた説などもあるそうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これを経営哲学と解釈して、座右の銘とする経営者も多いようですね。
変えることのできるもの と 変えることのできないもの
貴方の変えることのできるもの と 貴方の変えることのできないもの
生活の変えることのできるもの と 生活の変えることのできないもの
仕事の変えることのできるもの と 仕事の変えることのできないもの
世間の変えることのできるもの と 世間の変えることのできないもの
人生の変えることのできるもの と 人生の変えることのできないもの
神様に頼ってないで、たまには、自分で数えてみましょう。
きっと、気付くはずです・・・
真理は、変えることのできないものの中にある、と。
熟した果実がいつも落ちるおそれがあるように
生まれた人はいつでも死ぬおそれがある。
感興のことば <ウダーナヴァルガ> 無常11
生まれたばかりの赤ちゃんであっても、熟した果実。
生意気盛りの横着なクソガキであっても、熟した果実。
要領よく人を信じない新社会人であっても、熟した果実。
リストラされ職が容易にみつからない年になっても、熟した果実。
自分で用意した天下り先に再就職する年になっても、熟した果実。
平均寿命を超えたとしても、熟した果実。
すべて、熟した果実。
生まれたときに、既に、熟した果実。
エリート官僚も ヤクザも 坊主も キャバ嬢も ニートも
健康自慢であっても 幸せのような気がしていても
すべて、熟した果実。
生まれたときに、既に、熟した果実。
投稿日時 23:19
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
「毎朝、お初をお供えして、お茶と水をあげて、線香をたてて、手を合わす。
ご先祖様にじゃないよ、親父とお袋にだよ、俺が手を合わせるのは。
もう、親が死んで33年だよ。俺も、もう間もなく70さ。
いつお迎えが来ても、おかしくはないさ。覚悟はしてるよ。
お恥ずかしいけど、独り身でさ。結婚はしたんだけど別れちゃってね。
幸い、ガキもできなかったから。
33年の区切りっていうか、
なんだか、お坊さんにお経を読んでもらいたくなってね。
悪いけど、うちまで来てお経をあげてもらえないかな?
少し、遠いけれどお願いします。」
・・・しわがれ声だけれども、穏やかな響きある人から電話があった。
自宅でのお勤めを終えての茶飲み話。
毎朝、亡き母を思い、亡き父を偲ぶ。
何かあれば、母に打ち明け、父に頼る。
頂き物があれば母に見せ、季節になれば旬の物を父にすすめる。
若い頃、親の意見など耳も貸さず、家を飛び出したけれども・・・
今だからこそ、この時が持てた。こうして、この形で話しができる。
豊潤な祈りの時間。
優しさに満たされたあたたかな時間・・・孝順の心。
倶会一処<くえいっしょ>は、『阿弥陀経』にある言葉。
ご縁の深い者たちが、ともにひとつの場所で出会うという意。
ひとつの場所とは、お浄土の事らしいけれども・・・
お浄土って、遠くにあるような気がするかもしれないけれども・・・
今のあなたなら、おわかりでしょう。
そう、いま・ここ。いま・ここ。
世間虚仮 唯佛是真
聖徳太子『上宮聖徳法王帝説』
世間は、移り変わってゆく儚いもの。
世間の法とは、その国の法律、慣習、そして、常識。
これらは、所詮、一時の位であり、本当に頼るべき物ではない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
京都新聞 5月25日
天台宗総本山の延暦寺(大津市)で指定暴力団山口組の歴代組長の法要が営まれた問題で、同宗トップの渡辺恵進天台座主が25日開かれた臨時宗議会で「誠に遺憾であり、天台座主として憂慮に堪えない。深く反省し、不惜身命の決意で全国の檀信徒や一般社会の信頼回復に取り組んでほしい」と述べた。同宗の象徴である天台座主が本山の不祥事で遺憾の意を表明するのは異例。
宗議会では延暦寺の代表役員の執行(しぎょう)を引責辞任した今出川行雲氏が「故人を回向するのに差別すべきでないと法要を引き受けたが、施主や参列者に配慮を欠き、結果として暴力団の資金集めなどに利用された。誠に申し訳ない」と陳謝した。濱中光礼宗務総長も「開宗1200年という節目の年に、宗政を担う者としてざんきに堪えない」と再発防止と意識向上を訴えた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
滋賀県警曰く、
暴力団の法要は、純粋な宗教儀式ではなく、資金集めと勢力誇示であることが多い。香典という名目で数千万円のお金を集めた、とのこと。
最近は、ずいぶんと、佛法が世法にひよるなぁ。
法律に守られて生活しているのも事実だけれども・・・
投稿日時 01:19
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
居酒屋にて、酔客の定年間近のおっさん。 私の格好を見て、坊主と思ったのでしょう。私は、どこに行くのも作務衣ですから・・・っていうか、作務衣と法衣しか、持っておりませんが。 あのさ・・・ 葬儀社ってのも、ピンからキリまであるんだってね。 ひどいのもいるんだってね。気をつけなけりゃ、…
投稿日時 21:20
カテゴリ:
僧侶的 いま・ここ,
法話
by houe_admin
ニルヴァーナとは、煩悩の火を吹き消した状態、つまり、涅槃の事。
そこは、寂しく暗い世界ではなく、
煩悩が転化され、慈悲や智慧となって動き出す活溌溌地の真実の世界。
人は、自らの死をもって、完全なるニルヴァーナを得る。
たとえ、無残に命を落とすとも
たとえ、蔑みの中に死を迎えようとも
たとえ、いかに心残りがあろうとも
たとえ、この世に形として生まれ得なくとも
たとえ、わが親に殺められようとも
たとえ、わが子に虐殺されようとも
たとえ、見ず知らずの者から殺害されようとも
救い難いその状況において、ひとすじの光明は・・・
その人は、今、完全なるニルヴァーナにある事。
その人の死を完全なるニルヴァーナと観る事ができれば・・・
その人の骨を完全なるニルヴァーナと信じる事ができれば・・・
5月 12日 方便
方便とは、 梵語ウパーヤ の漢訳。 近づく、 到達するの意。 巧みな方法を用いて衆生を導くこと、 真実の法に導くための仮のてだてとしての教え、 巧みな教化、 差別<しゃべつ>の事象を知って衆生を利益<りやく>する智慧などの意味があります。 方は正しい、便は手段という意から、方便。…
ご葬儀を終えて、設斎での事。 喪主:「本当にありがとうございました。 とても、素晴らしいお経で、家族も親戚も喜んでおります」 愚僧:「お経の意味がおわかりになられましたか?」 喪主:「はい、何にもわかりませんでした。 でも、そのお経の時間が、素晴らしかったです。」 愚僧:「?」 …
佛、沙門に問う「人の命、いくばくの間にか在る」 対えていわく「数日の間なり」 佛いわく「汝、いまだ道を知らず」 また一の沙門に問う「人の命、いくばくの間にか在る」 対えていわく「飯食の間なり」 佛いわく「汝、いまだ道を知らず」 また一の沙門に問う「人の命、いくばくの間にか在る」 …